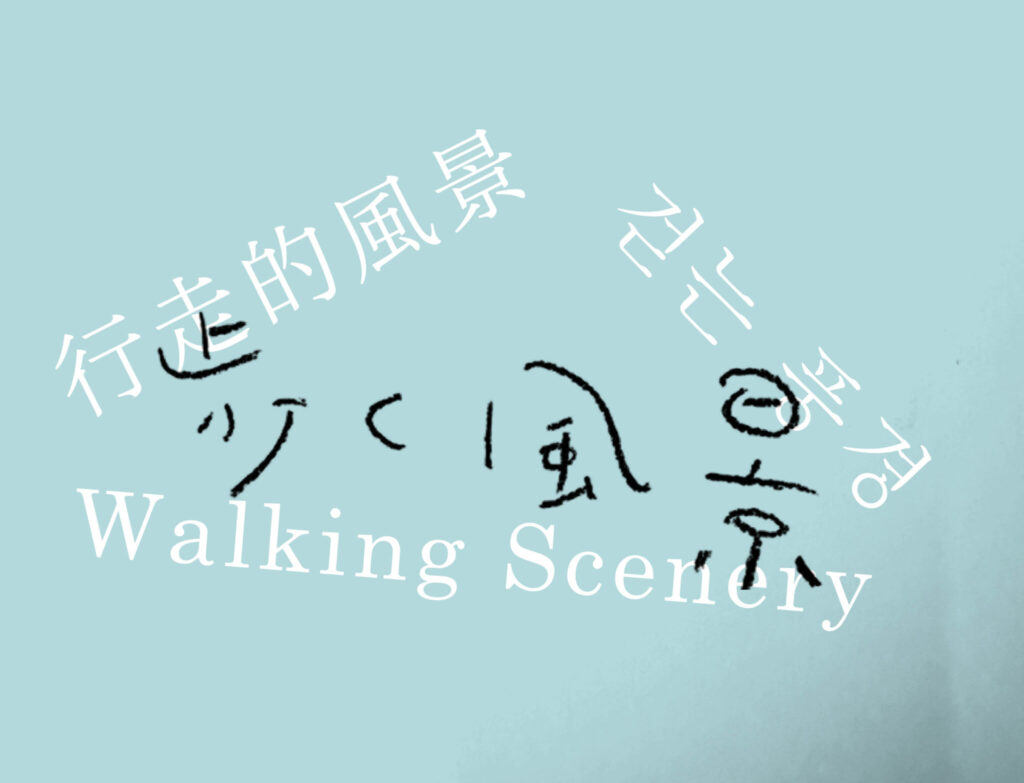20250501
人の記憶は頭の中にあるのではない、それは風景の中にある――。
人の目を通して記憶・記録される風景は、土地の歴史の蓄積であると同時に、個人の記憶を呼び起こすトリガーでもある。それは、過去と現在をつなぐ一つのツールだ。中でも「歩行」という、より個人の身体につながる運動を通して見る風景は、上空からの俯瞰とも、自動車や列車の車窓とも異なる、個人の思考やひらめきに直結するものとして、多くの創作や思索を生み出してきた。歩くことの創造性は、レベッカ・ソルニットの『ウォークス 歩くことの精神史』で語られている通りだ。
一方、東京をはじめとする東アジアの都市部においては、絶え間ない開発により、日本では約40年、中華圏になると早いところは20年ほどで建て替えられ、風景は短期間に変化する。これが、社会が土地の記憶を忘却することにもつながっていると言えよう。しかし、アジア地域は戦後から近過去まで激動の歴史を辿ってきた。とりわけ近隣に位置する韓国では1987年に民主化宣言が発せられ、台湾では同年まで戒厳令が続き、その後急激な都市化が進んだ。つまり、現在のように高層ビルが立ち並ぶ風景になってから30~40年しか経っていないが、隙間には今も過去の片りんが残っている。
「歩く風景」は、温又柔(台北)、瀬尾夏美(東京)、パク・ソルメ(光州)と、出自の異なる3人の女性アーティストが、東京ともう一つ場所を歩き、土地の風景を通して戦後史と今を結び、表現を媒介として語り継ぐ試みである。東京、台北、釜山をそれぞれの作家が訪れ、歩き、その土地の未完の戦後史に触れる。そして、各地ではワークショップを開催し、参加者と共にどのように歴史のバトンをつないでいくかを語り合う。最後に、そこから生まれた創作を、朗読やパフォーマンスの形で公演する。書かれるテキスト自体も創作であると同時に、その「ことば」は、いずれまた別の表現の種になるはずだ。
かつて日本が植民地支配をしていた韓国や台湾と、近現代史を共有し語り合っていくことは容易ではない。一方、ウクライナやガザをはじめ、世界各地で戦争や紛争は起き続けている。だからこそ、近過去の各地の歴史を学び、それが今の私たちにどう影響し、未来につなげていくのかを考える機会が必要だ。創作は、土地固有の問題を描くと同時に、他者も共感可能なものにもなり得る。「歩く風景」は、旅人が歩きながら体に沁み込ませていく風景≒歴史を、芸術という形でまた別の人に送り届ける、ささやかだが確かな共有の方法へと育っていくだろう。
主催:株式会社soon
参加作家:温又柔、瀬尾夏美、パク・ソルメ
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[スタートアップ助成]
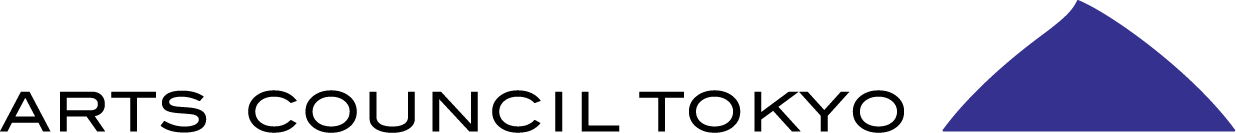
開催日程:
2025年5月:台湾リサーチ&ワークショップ(温又柔)
2025年6月:東京リサーチ(パク・ソルメ)
2025年8月:釜山リサーチ&ワークショップ(瀬尾夏美)
2025年12月:参加作家による朗読パフォーマンス+公開シンポジウム @東京(場所未定)
日本、台湾、韓国、それぞれの出自をもつ女性アーティストたち
3名の作家は、各々これまで「歩く」ことで思索を重ね、表現につなげてきた。
台湾・台北で生まれ、3歳の時に家族で日本に移住した温又柔さんは、約40年間住み続けてきた東京の風景が再開発によって激変しつつあることを契機に、自らの幼少期にあたるバブル前後に建てられたビルや湾岸の風景に、初めて郷愁に近いものを覚えたという。同時に、台北に残る日本統治時代の建物がある風景には、安心感と共に複雑な思いも抱く。この気づきをもとに、2021年以降アートプロジェクト「住むの風景」に参加し、東京と聞いて思い出す、記憶に長く留まっている風景を歩き続けている。
東京出身で、東日本大震災以降の約10年間を陸前高田や仙台で過ごした瀬尾夏美さんは、毎晩散歩をしながら思ったことをツイッターに書き、それらを2017年に『あわいゆくころ』(晶文社)という一冊にまとめ上げた。現在は、広島や沖縄における戦争の記憶継承にも関心を広げ、ワークショップやフィールドワークを続けている。彼女の表現の核には、旅人として見知らぬ土地を歩き、出会った人々の言葉を紡ぐことがある。
韓国・光州出身のパク・ソルメさんは、日々散歩をすることが創作には欠かせないと語っている。日本語にも翻訳された『未来散歩練習』(2023、白水社)は、主人公が釜山に仮住まいを設けて町を歩き、目にする風景の中で、光州事件(1980)に端を発した釜山アメリカ文化院放火事件(1982)が語られていく。パクさんは引き続き釜山に興味をもっており、同地を舞台にプロジェクトを進める。
「失われつつある都市の風景のなかで、歴史とはすでに出来上がっているものなのだと信じて疑ったことのなかった私は、誰かが囁くのを感じる。
――仮に、あなたがある風景のなかにいて居心地よく感じているとしたら、あなたはまだ、その風景の背後に控える未完の歴史を充分には知らない。
そう、未来というものがあるかぎり、私たちの前をさっとかすめて過ぎ去るどんな歴史も、まだ部分的な真実でしかない。」
温又柔「未完の歴史と向かい合うために」より抜粋
歴史はこれまで大文字の物語を正史とし、個人、特に女性の視点はこれに乗らないオルタナティブとして扱われてきた。参加作家たちは、この状況も理解したうえで、東アジアの移りゆく風景から土地の記憶を掘り起こし、未来につなげようとしている。「歩く風景」では、都市の光景が刷新され続けるアジアにおいて、アーティストたちが歩き記憶していく風景を起点に、近過去を見つめ直し、新たな表現として共有できる形を模索していく。それぞれの作家による小さなナラティブが積み重なった時、そこには私たちが近い地平で語り合える、新たな場が生まれるかもしれない。